-
-
-
企業ニュース
アクセスランキング-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
働きやすい企業ランキング
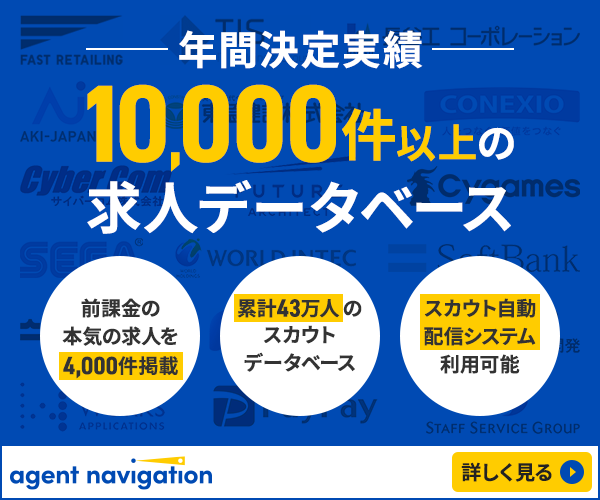
-
「Z世代は主体性がない」と嘆く上司は勘違いしている? 若手のやる気を引き出すための3ステップ | 企業ニュース
| キャリコネ 口コミ・評判の情報サイト

「Z世代は主体性がない」と嘆く上司は勘違いしている? 若手のやる気を引き出すための3ステップ NEW
私が主催している管理職向けのマネジメント研修では、受講生からZ世代の部下に関する悩みをよく聞きます。特に多いのが、「主体性がなさ」を嘆くもので、
「Z世代の若手社員は指示をしないと、動いていくれない」
「聞かないと、報連相してこない」
「仕事が終わっていないのに、帰ってしまう」
といったものになります。
今回は1990年代半ばから2010年代前半に生まれたZ世代の特徴を踏まえながら、どうすればやる気を引き出せるのか、管理職ができることについて考えていきます。(文:働きがい創造研究所社長 田岡英明)
Z世代は本当に受け身なのか?
そもそも、Z世代は本当に受け身なのでしょうか。ここで、戦後から現在までの学校教育の流れを見ると、意外なことが見えてきます。
1960年代の高度経済成長時代は暗記型の教育が主流で、教師が伝えたことをいかに覚えられるかが求められました。やがて1980年代に入りバブルで日本が豊かになると、暗記教育からの脱却が図られ、自ら学び自ら考える力や問題解決能力を育む総合学習が創設されました。
続く2000年代には「ゆとり教育」が導入され、その後、学力低下への懸念からその見直し(揺り戻し)も行われました。その過程でも、生徒が自ら課題を探究する「総合的な学習の時間」は一貫して強化されてきました。
そして現代の2020年代に入ると、科学・技術・工学・芸術・数学といった分野を横断的に学んで課題解決を目指す『STEAM教育』が提唱されるなど、生徒の主体性を重んじる流れはさらに加速しています
以上のような流れを見てみると、Z世代は少なくとも学校では主体性を伸ばす教育を受けており、必ずしも最初から受け身ではないことが想像されます。では、なぜ入社して仕事を始めると受け身になってしまうのでしょうか? また、管理職からすると、受け身に見えてしまうのでしょうか?
若手の心を理解し、3つのステップで若手のやる気を引き出す
研修で若手社会人を関わると、次のような悩みを聞くことがあります。
「希望と違う配属。もう辞めたい」
「入社前に描いた理想と現実にギャップを感じる」
「自分が必要とされている実感がない」
「このままでは成長できない。時間もないし焦る」
「 旧態然とした仕事の進め方についていけない」
「ほめてくれれば頑張れるのに…そうしてくれない」
「地味な仕事ばかりでイヤになる」
「いざ働き始めたら自信が持てない」
「将来、目標にしたい先輩がいない」
悩みの具体的な内容は人それぞれではありますが、入社前に思い描いていたイメージとの違いや、成長実感への不安に戸惑っている様子がうかがえます。
そんな若手の心を理解し、管理職としては次の3つの関わりを意識していきましょう。
(1)入社前後のリアリティショックを緩和する
SNSネイティブであるZ世代は、世間の問題に敏感で仕事の目的や意義を重視する傾向があります。入社前にこの会社に入ったら「社会に貢献できる仕事ができる」とか「仕事を通して成長し、世の中の役に立てる自分になりたい」といった思いを持っています。
しかし、現実は下積みの仕事であることが多く、目の前の仕事に入社前に抱いていた思いとのギャップを感じています。管理職としては、まずは傾聴の姿勢を心がけ、その思いを受け止めていきましょう。
(2)目の前の仕事の本質とキャリアとの繋がりを理解させる
組織の中にある仕事で意味のない仕事は無いことや、担当している仕事が意味のあるものであることを日頃のコミュニケーションや1ON1の中で伝えていく必要があります。そして、目の前の仕事に集中した結果として次のステージに進めることや、様々な経験を経ることで思い描くキャリアイメージに到達していくことを伝えていきましょう。
目の前の仕事とキャリアイメージの繋がりを感じられれば、若手のモチベーションは回復していきます。
(3)仕事を通じた成長実感を醸成する
Z世代を中心とした若手は会社を選ぶ際に「自らの成長が期待できる」といった点を重視しています。
なので会社に入って成長実感がないと、飽食の時代で我慢をしないで育ってきている若者は、すぐに諦め感を抱いてしまいます。この諦め感に苛まれる前に、成長実感を育んでいく必要があります。ポイントは、小さな成功体験を数多く設計することにあります。小さく刻んで仕事を任せ、やり遂げさせ、成功のポイントを毎回振り返らせていきましょう。
以上今回は、主体性の無さに問題を感じるZ世代の心の中を理解し、やる気を引き出すポイントについてご紹介して参りました。忙しい中、こまめなコミュニケーションが求められますが、その関わりが高い成果を出す組織醸成につながると信じて取り組んでいってください。