-
-
-
企業ニュース
アクセスランキング-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
働きやすい企業ランキング
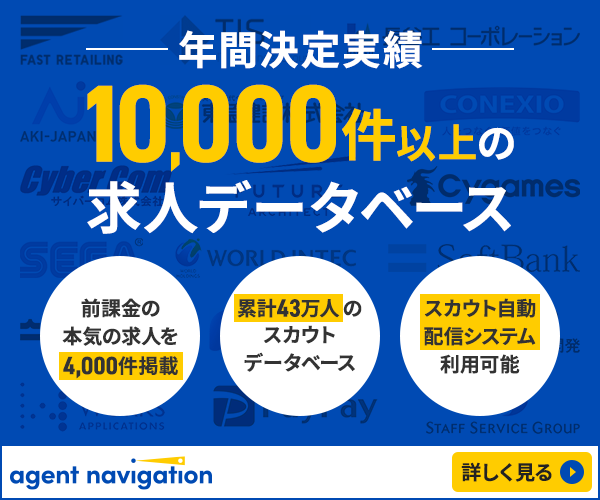
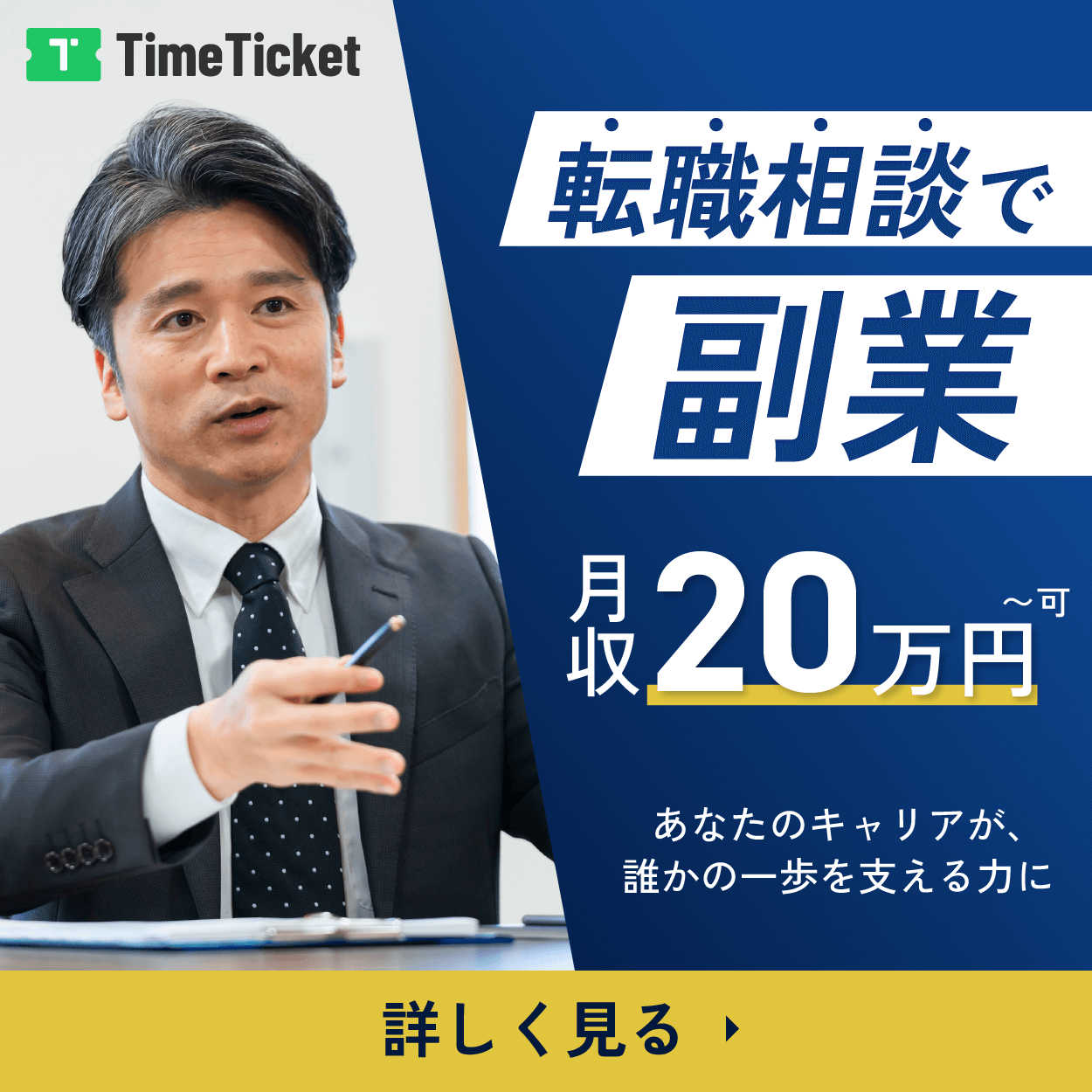
-
上司は部下に「マイナス評価」をどう伝えるべき? 今後のやる気を挫かない方法 | 企業ニュース
| キャリコネ 口コミ・評判の情報サイト

上司は部下に「マイナス評価」をどう伝えるべき? 今後のやる気を挫かない方法
私が担当する管理職研修では受講生から、
「部下に良い評価を伝えるのは問題ないのですが、マイナスの評価を伝える際に気を使い過ぎてしまって、伝えたいことが伝えきれません。どのような伝え方が効果的なのでしょうか?」
といった質問をいただくことがあります。確かにこれは難しい問題です。今回は、部下のやる気を挫かないで、マイナスの評価を伝えていくポイントについてご紹介してまいります。(文:働きがい創造研究所社長 田岡英明)
「目標達成に向けて頑張ります」→その後、上司のフォローなし これで納得できる?
多くの企業がメンバーの成長支援と査定といった観点から、評価制度を導入しております。その期に達成したいことをメンバーと握り、半年から1年の期間で評価をしていくといったものが一般的です。
しかし、1回の目標設定面談と1回の評価面談をベースに運営されていることが多く、実際の現場では部下の成長にうまく繋がっていないと言われることが多いようです。なぜなら笑い話のようですが、次のような現場が多く存在するからと言われます。
目標設定時(部下):「今期は、この3つの目標達成に向けて頑張ります!」
目標設定時(上司):「よし、頑張ろう!私も応援しているからね。」
期中:決めた目標に対するコミュニケーションがあまりない・・・
評価面談時(上司):「よし、そろそろ評価面談をするから、用意しておいてくださいね!」
評価面談時(部下):「やばい!今期はどんな目標立ててたっけ? しばらく見ていなかった……とりあえずうまく繕っておこう!」
皆さんの状況はいかがでしょうか?このような不毛な評価制度は回したくはないですよね。では、どのようなポイントに気をつけて評価制度を運営していけば良いのでしょうか?
「マイナス評価」でも部下のやる気を挫かないために 3つのポイント
マイナス評価でも部下のやる気を挫かない評価制度を運営していくためには、次の3つのポイントを押さえながらコミュニケーションを取っていく必要があります。
1つ目のポイントは、目標設定時の認識合わせと納得感醸成です。目標を設定する際には、キャリア目標をベースに、現在の仕事で満足しているところと不満足なところ、現在の役割でうまく行っているところと、うまく行っていないところを事前に聴取するようにしましょう。
そして、聴取した内容をベースに部下に目標設定を任せていくのです。そうすることで目標への納得感が増していきます。また、上司自身の譲れない評価基準や拘りも同時に伝えておけると、評価面談時の更なる納得感につながるでしょう。
2つ目のポイントは、プロセスへの上司の関わり実感の醸成です。期中のプロセスに上司自身の関与がないと、評価が良かった場合はいいですが、評価がマイナスとなった場合、部下の心には、
「何の支援もしてもらえなかったのに、プロセスを見ないで結果だけでこんな酷い評価をされるんだ……」
といった不満だけが残ってしまいます。期中のプロセスに上司が関わっている実感が養われていれば、「上司もしっかり支援してくれたけど、この達成度では、この評価は仕方がないな……次は頑張ろう!」といった前向きなものになっていきます。
3つ目のポイントは、内省を促しながら評価を伝えることです。マイナスの評価に対し、
「今回の評価に対しての今の率直な感情は? その感情の原因はどんなもの?」
「どんな部分がうまくいかなかった原因だと思う?」
「今回の評価を、次にどう活かしていきたい?」
と現在の気持ちから、過去への振り返り、そして未来に向けての思い構築といった、内省を促す質問を繰り出していきましょう。人は、自身の中からの気づきによって成長していきます。
以上、今回は、部下のやる気を挫かないマイナス評価の伝え方についてご紹介してまいりました。マイナス評価を伝える際に、コミュニケーションスキルに走り過ぎず、効果的な評価制度を回すといった全体感の中で、今回の内容を活用してみてください。