-
-
-
企業ニュース
アクセスランキング-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
働きやすい企業ランキング
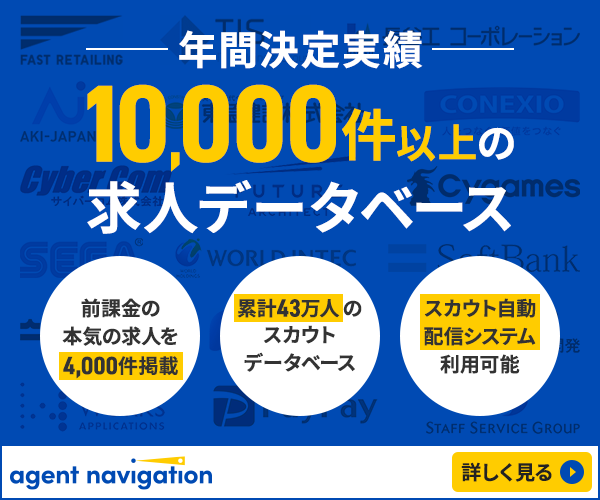
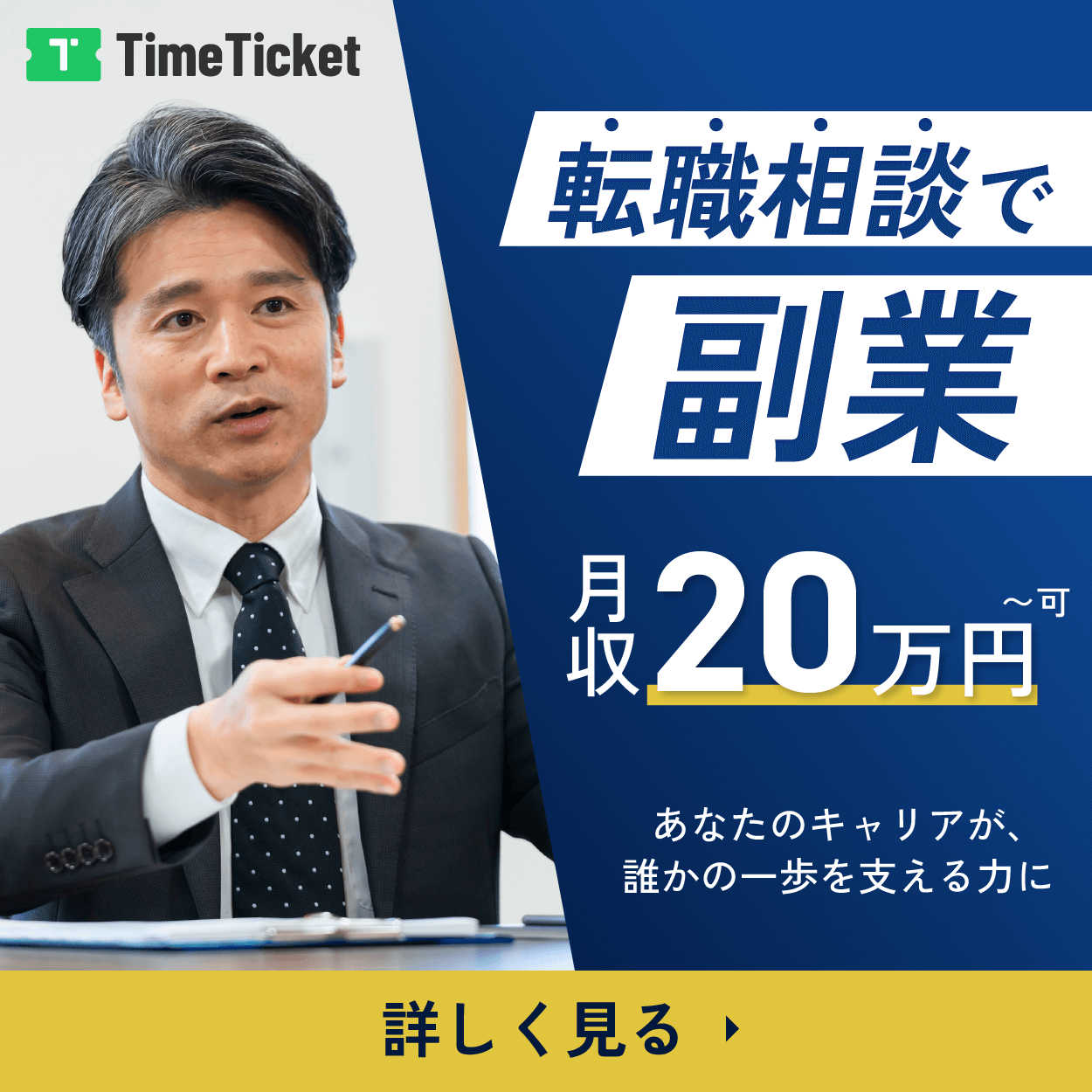
-
バーバーリー頼みが裏目に? 三陽商会にみるライセンス事業のリスク | 企業ニュース
| キャリコネ 口コミ・評判の情報サイト

バーバーリー頼みが裏目に? 三陽商会にみるライセンス事業のリスク
1月26日に新聞各紙が朝刊で報じた三陽商会の希望退職者募集の報道が、アパレル業界で波紋を広げている。その内容は各紙とも、ほぼ次のような内容だ。
「アパレル大手の三陽商会は、希望退職者を230人程度募集すると発表した。全従業員の1割強に当たる。同社が希望退職者を募集するのは初めて。消費が冷え込み、業績低迷が続いており、コスト削減を図る狙い」。
ベタ扱いの簡単な記事だったが、これを読んだ業界関係者の一人は「いよいよ始まったかと思った」と言う。同社の希望退職者募集は、これから幕を開ける“本格的リストラの序曲”と見る業界関係者が多いからだ。
三陽商会といえば英ブランドの「バーバリー」を扱っていることで知られる。1970年に英バーバリー社とライセンス契約を締結。以降、バーバリーブランドの衣類など各種をほぼ独占販売する格好となった。
同社は戦時中に使用された暗幕をレインコートに再生して販売。そのヒットでレインコートの大手として台頭し、レインコート専業から総合アパレルに成長した。バーバリーは、そのけん引役となったため、同社は英バーバリー社とは切っても切れない仲にある。
ところが、このバーバリー頼みの経営が、今や同社を苦しめる原因になっているという。そこで、今回は同社について、キャリコネに寄せられた社員の声から内情を見るとともに、希望退職の裏側を探ってみよう。
◇
本社との格差で士気が低い販売現場
三陽商会の平均年収ランキングは、業界10位前後で、大手にしては意外に低い。特に、同社を支えているはずの販売現場から待遇に不満の声が目立つ。例えば、店長の女性社員(20代後半)は、次のように話している。
「8年間働いて最終的な年収は300万(店長5年)。服や接客が好きでやりがいが見いだせればやっていけると思うが、仕事量や求められるスキルには似合っていない」
また店員の女性契約社員(40代前半)はこう言う。
「入社時に決まった月収はほぼ変化なし」
20代前半の女性契約社員も同様の意見だ。
「正社員も現場は給与がものすごく少ない。売り上げアップや月予算を達成しても、報酬や金一封は一切ない」
これは2010年から導入された、店舗の売り上げを店舗従業員の給与に反映させる「店舗予算制」に起因しているようだ。同社関係者は次のように明かしている。
「本社勤務の正社員と現場勤務の正社員・非正社員では、月給も賞与もかなりの開きがある。会社は『業務が違うから』と説明しているが、そんな子供だましで現場は納得しない。店舗予算制は、売り上げ不振が続いているため、人数が多く経費削減効果が高い、販売現場の給与削減策にすぎない」。
またキャリアパスの閉鎖性も現場の閉塞感を強めているようだ。例えば、店員の女性契約社員(20代後半)は、こう述べている。
「店舗スタッフが総合職にはほとんどなれない。社内公募はない」
別の女性契約社員(20代前半)も、こう打ち明ける。
「販売から本社勤務への出世はかなり難しいと思う。 これは面接の時にも面接官にかなり狭き門だと言われた。10年以上働いて店長止まりの人はたくさんいる」
◇
契約見直しや売り上げ低迷で囁かれる「15年危機説」
三陽商会にとって、バーバリーのライセンス事業は「売上高の半分以上を占める基幹事業。利益率も高いドル箱」(アパレル業界関係者)
だった。しかし、今はドル箱どころか、危機に直面している。
理由の1つが「ライセンス契約の見直し」だ。70年に初めて締結したバーバリーのライセンス契約は99年に更改。その時のライセンス期間は20年だった。しかし、09年に英バーバリーから契約見直しを要求され、ライセンス期間は20年から15年に短縮。三陽商会はライセンス料の値上げまで呑まされた。
もう1つの理由は英バーバリー社の日本への直接進出だ。09年、同社は都内の表参道を皮切りに全国各地に直営店を出店し始めた。その結果、「バーバリー社はブランド定着の役割を終えた三陽を外し、自ら儲かる日本事業を本格的に展開する」との見方がアパレル業界で強まった。
同時に、ライセンス期間が2015年6月に満了することから「三陽の15年危機説」も囁かれるようになった。15年以降のライセンス契約の更改について、三陽商会は「交渉中」としか説明していない。このことも業界内で「三陽の15年危機説」に拍車をかけた格好だ。
さらに、売り上げ不振も追い打ちをかけている。
三陽商会は売り上げの85%を全国の有名百貨店での販売に頼っているが、販売力は年々下降。一方で、専門店、直営店などの非百貨店ルートの開拓は遅々として進んでいない。
その影響のためか、09年12月期連結決算では52億円の営業赤字に転落。10年12月期は24億円の黒字を回復したが、11年12月期は実質横ばいだった。12年12月期は45億円の黒字見通し。しかし、「バーバリーの穴を埋められる自社ブランドが育っておらず業績回復の力は弱い」と、アパレル業界のアナリストは分析している。
◇
ブランドが市場に浸透すれば“お払い箱”
三陽商会に限らず、欧米ブランドからライセンス契約を一方的に解消され、窮地に陥ったケースは多い。その典型が98年に独アディダスからライセンス契約を打ち切られたデサントだ。
当時のデサントは売り上げの40%強、営業利益の半分近くをアディダスのスポーツ用品が占めていた。だが、28年続いた契約を突然解消され、その影響で01年から3期連続の営業赤字を計上した。
この他、サザビーリングは、05年に仏アニエスベー、オンワード樫山は、07年に米ラルフ・ローレンからライセンス契約を打ち切られている。その後、仏アニエス、米ラルフともに「儲かる日本事業」を自前で展開した。
「アパレル業界にはライセンス事業を好む風潮が強い」。業界関係者は、こう指摘する。それは、売上高の10%が相場といわれるライセンス料を払うだけで、有名ブランドを製造・販売できるからだ。
中小企業が多い日本のアパレルメーカーにとって、ライセンス事業は開発の投資を行わずにブランド展開ができるため、大きな魅力で積極的な企業が多い。
一方、ブランド供給側は冷静だ。そうしたメーカーを「リスクを冒さずにブランドの浸透と市場拡大を図る水先案内人の存在に過ぎないと見ている。ライセンス料だけの付き合いなので、簡単に関係を打ち切る」(業界関係者)という。
こうしたリスクが、今回、三陽商会のライセンス事業で改めて浮き彫りになった格好だ。バーバリーに頼り過ぎたともいえる同社。バーバリー抜きの成長戦略を描けるかが問われている。
【その他の企業徹底研究の記事はこちら】