-
-
-
企業ニュース
アクセスランキング-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
働きやすい企業ランキング
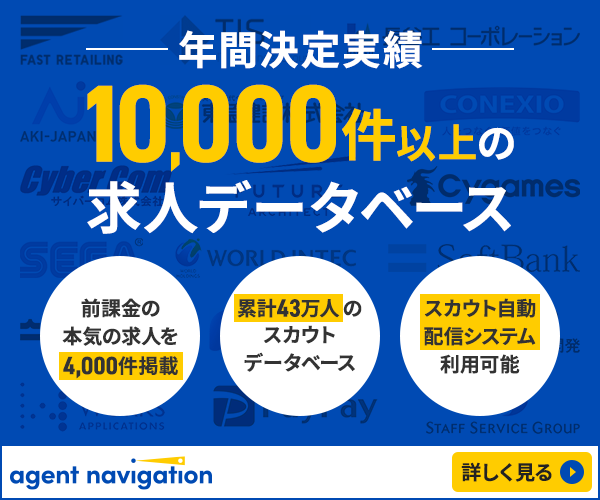
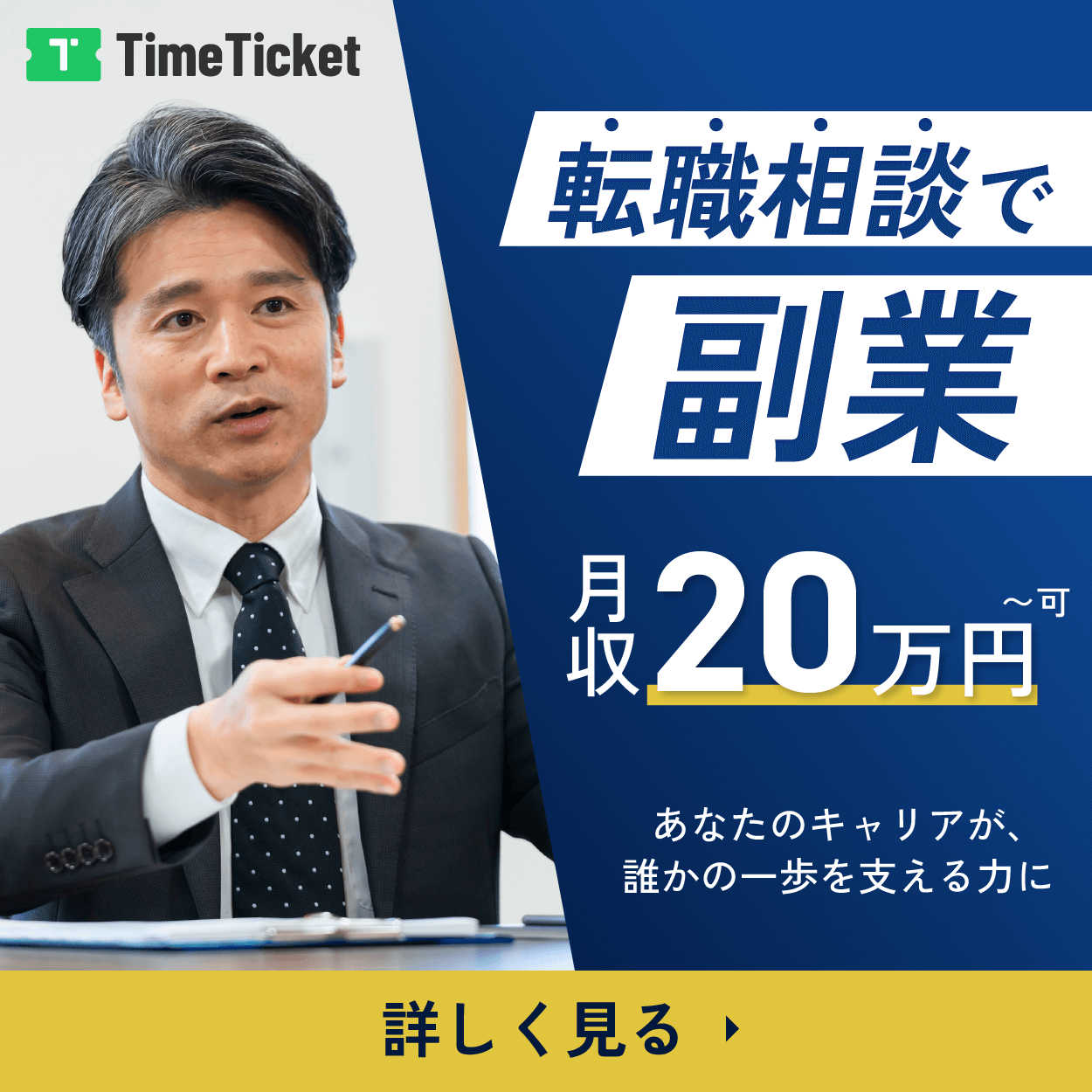
-
ブラック企業が行き着く「ホワイト化」 本当に信じられるか? | 企業ニュース
| キャリコネ 口コミ・評判の情報サイト

ブラック企業が行き着く「ホワイト化」 本当に信じられるか?
ある40代男性の勤めるA社では、最近役員がしきりにそう言う。同社は予備校を経営しているが、ここ数年は業績悪化を理由に賞与が出ていない。
ブラック企業が行き着くところまで行くと、急に経営陣が汚れた衣類を漂白するように、「ホワイト企業化」を図る場合がある。「ムチ」ばかりくれていた社員に「アメ」を出し、なんとかつなぎ止めようというのだ。
「賞与を手にするまでは信じませんよ」
A社もそうなのでは、と男性と言う。パワハラ、サービス残業、不当解雇と、同社はブラック労働のオンパレードだった。その結果、有力な社員が続々と辞めてしまったから、
とその噂をいぶかしむ。
ただ、本当に賞与が出るようになったとすれば、労働環境の抜本的な改善を図っている最中であるかもしれない。そうなれば、労働者としては「働きやすくなる前兆」であって、このまま労働環境が改善し続ければ、と願う社員もいるだろう。
ブラック企業アナリストの新田龍氏はキャリコネ編集部の取材に対し、ブラック企業に改善が見られる理由について「人心の入れ替わり」を挙げる。つまり、権限を持っている人が交代したり、その人が「こういう経営ではやっていけない」と心変わりした場合に、制度や環境が改善されることがあるという。
人がごっそり辞めて「残業代が支給された」
広告代理店B社に勤める30代男性社員も、人がごっそり辞めた2か月後から、急に残業代を出すことが発表されたという。その前に、「このままじゃやばいな…」と役員がつぶやいていたのを聞いた。
残業代はそれほど多い額ではないが、出ないよりは良い。仕事自体は厳しいため辞める人はいるが、それでも以前に比べると離職率は減った。
ほか、「ノー残業デー」の導入や、営業目標を達成したチームに報奨金が支給されたりと、社員に配る「アメ」は多様にある。たしかに経営陣からすると、熟練した社員に辞められるのは痛手だ。
ただ、「喉元過ぎれば熱さ忘れる」ではないが、社員の定着率が少し安定すると、また「ムチ」ばかりの労働環境に「ブラック化」してしまうこともあるという。新田龍氏は指摘する。
労働者にとって、自分が勤めている会社が「沈みゆく舟」なのかどうかを判断するのは重要だ。労働環境はその指標のひとつになる。この冬は「賞与が増えた」といった報道もあるが、その本質をしっかり見極めたいところだ。
あわせてよみたい:ブラック企業を「求人広告」で見抜く方法とは?