-
-
-
企業ニュース
アクセスランキング-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
働きやすい企業ランキング
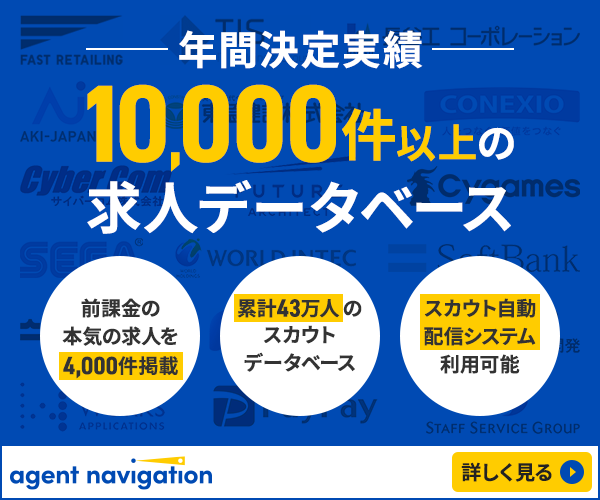
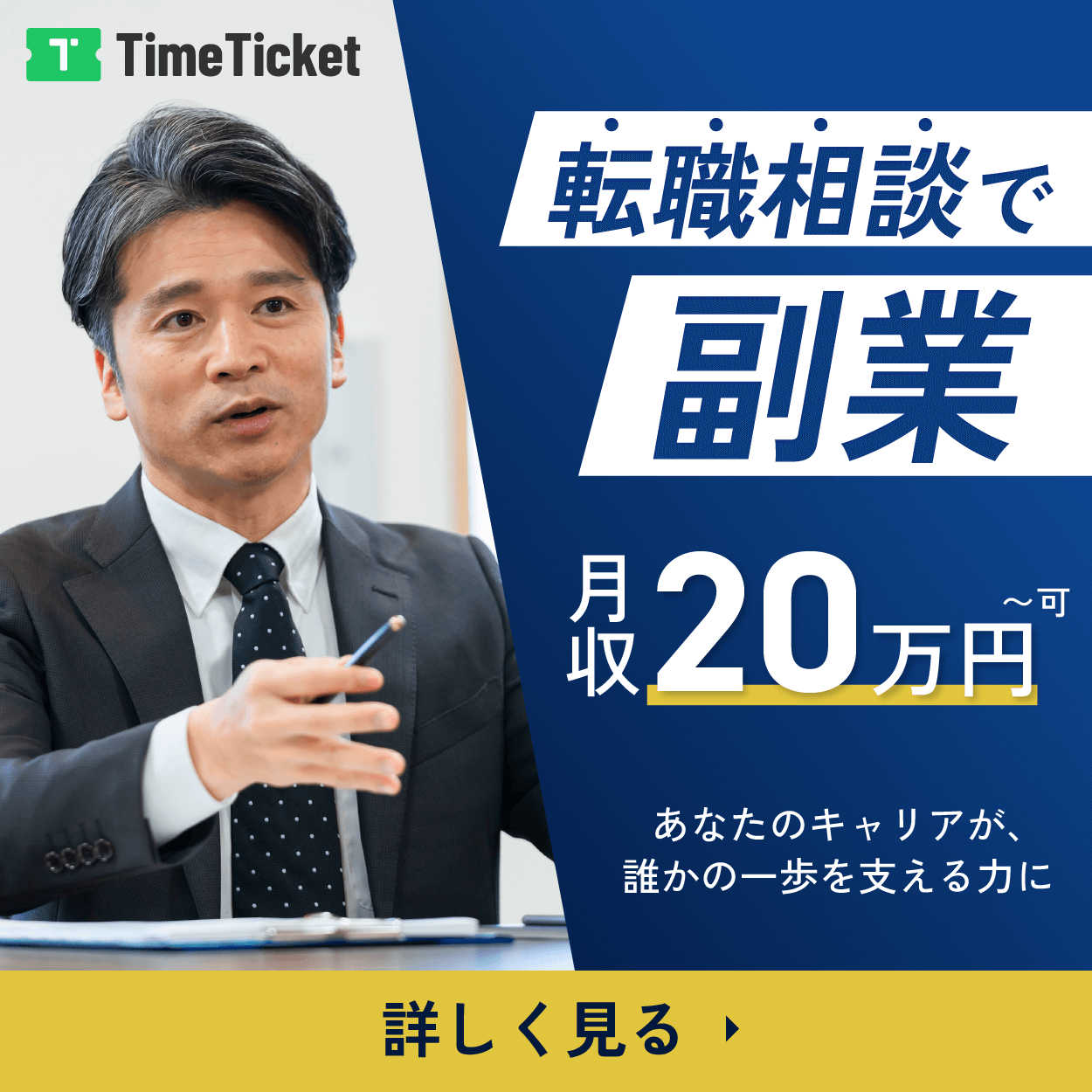
-
外国人労働者の「受け入れ」拡大 「すんなり」か「トラブル誘発」か? | 企業ニュース
| キャリコネ 口コミ・評判の情報サイト

外国人労働者の「受け入れ」拡大 「すんなり」か「トラブル誘発」か?
1月20日、政府は競争力強化や国際展開の推進について審議する「産業競争力会議」を開催し、外国人労働者の受け入れ拡大案を今後の検討方針として盛り込んだ。
背景にあるのは、深刻な人手不足だ。アベノミクスによる景気回復への期待感、東京五輪に向けた施設建設などで人材需要は高まっているものの、少子化等の影響で生産年齢人口(15歳以上65歳未満の人口)は減少し続けている。
「外国人材活用のあり方」を検討
国勢調査によると1995年の生産年齢人口は約8700万人だったが、2012年には約7900万人にまで減少した。国立社会保障・人口問題研究所は、2027年には生産年齢人口が7000万人にまで減少すると推計している。
同会議で配布された資料によれば、外国人労働者の受け入れ環境の整備、外国人技能実習制度の見直し、必要分野・人数を見据えた外国人材活用のあり方などを検討するという。
とはいえ、すんなりと外国人労働者の受け入れが進むかどうかは未知数だ。キャリコネの口コミを見ても、彼らをめぐる問題がいくつか見受けられた。まず目につくのは、言語の壁が生むコミュニケーションの問題だ。
今後、外国人労働者の受け入れが拡大するのであれば、言葉の壁はどの業界にとっても切実な課題になる。好むと好まざるとに関わらず、外国語スキルの重要性が増すことは間違いないだろう。
外国人教師は「休憩が2倍長い」?
また、日本人と外国人とで「待遇に差がある」という声もある。外国人が厚遇されている例と、日本人が厚遇されている例のいずれもあった。
業務内容や役職などに違いがないのに、国籍によって給与や福利厚生に差がついているというのであれば、やはり問題だろう。日本人と外国人の間で、社内トラブルが発生することも考えられる。
外国人上司だと「休みが取りやすい」メリットも
ただ、外国人と一緒に働くことがプラスになったという声もあった。外国語スキルが磨かれるという意見のほか、外国人上司のメリットを挙げている人もいる。
日本企業では、休みを取らないことが会社への貢献だと考える上司は少なくない。旅行会社「エクスペディア」の調査でも、日本の有休取得率は24か国中で最低の39%だ(2013年時点)。部下の休暇を「当たり前」と考えてくれる外国人上司は、日本人にとって新鮮に映るかもしれない。
政府は24日の関係閣僚会議で、2020年の東京五輪開催に伴う建設労働者の不足を見据えて、外国人労働者の受け入れを拡大する方針を確認したという。
あくまでも時限的措置とのことだが、こうした動きは遅かれ早かれ各界に広がっていくだろう。日本の労働力も労働環境も、いつまでも「ガラパゴス」であるわけにはいかないようだ。
あわせてよみたい:アメリカ人の美しき思い違い